解体工事の手順や流れを分かりやすくステップ別に紹介!
2024-07-09

解体工事は、古い建物を取り壊して、新しい空間を作り出す大切な作業です。
この作業をすることで、地域に新しい風をもたらし、新たな始まりを切ることができます。
しかし、解体工事はただの建物壊しではありません。
安全や環境保護に関する厳しいルールがあり、計画的に進めなければなりません。
この記事では、解体工事の基本的な流れや、ステップごとに注意すべきことを分かりやすく説明します。
具体的には、工事の準備から始まり、解体作業、片付け、そして最後の事務手続きまでをカバーし工事を進めるためのポイントもお伝えします。
家の解体工事、何から始めればいいのか不安ではありませんか?
特に費用がいくらかかるのか分からないと心配がつきません。
そんな時は、Webで解体費用相場がわかる「解体の窓口」を利用するのがおすすめです。
わずか1分でお住まいの解体費用の相場が分かります!
さらに、そのまま一括見積もりも可能です。
このサービスは東証上場企業が運営していますので、安心してご利用ください。
\営業電話一切なし!1分の簡単入力/
解体工事の手順と流れ
オレンジ色の枠線部分が、施主(自身)が手配などをする部分となります。
-
- 01解体工事会社の選定
- 信頼できる解体工事会社を見つけ、数社に絞り込みます。推薦やオンライン評価を参考にしてください。
-
- 02見積依頼
- 選定した会社に見積もりを依頼し、複数の見積もりを比較検討します。
-
- 03現地調査
- 解体工事会社が現地を訪れ、建物の状態を調査し、正確な見積もりを作成します。
-
- 04見積書の受け取り
- 調査後、詳細な見積書が提出されます。工事の範囲、費用、スケジュールなどが記載されています。
-
- 05契約の締結
- 見積もり内容に問題がなければ、契約を締結します。不明点があれば、契約前に確認しましょう。
-
- 06家財整理と処分
- 解体前に、不要な家財や物品の整理と処分を行います。
-
- 07各種届け出
- 解体工事に必要な届け出があれば、地方自治体に提出します。事前に必要書類を確認しましょう。
-
- 08ライフラインの停止
- 電気、ガス、水道などのライフラインを解体前に停止します。
-
- 09近隣への挨拶
- 解体工事による騒音やほこりが近隣に迷惑をかけないよう、事前に挨拶を行い、理解を求めます。
-
- 10解体工事の着工
- すべての準備が整ったら、解体工事が開始されます。
-
- 11工事の完了と確認
- 解体工事が終了したら、工事が計画通りに完了しているかを確認します。
-
- 12請求書の受領と支払い
- 工事完了後、請求書が発行されます。内容を確認した上で、支払いを行います。
-
- 13マニフェストの発行
- 解体工事で出た廃棄物の処理状況を記録したマニフェストが発行されます。
-
- 14滅失登記の申請
- 建物が法的に存在しなくなったことを証明するため、法務局に滅失登記を申請します。
この流れに沿って進めることで、解体工事をスムーズに行うことができます。
また、地域によっては手続きや必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。
解体工事会社の選定について

解体工事を進めるにあたり、最初に必要なのは信頼できる解体工事会社を見つけることです。
- インターネットでの検索: 地域名を含めて「解体工事会社」と検索し、情報を収集。
- タウンページや電話帳の利用: 地元の会社を探す古典的な方法。
- 見積もり比較サービスの活用: 条件に合う会社を効率良く見つける。
- 口コミや評判の確認: 実際の利用者の意見を参考にする。
- 相見積もりの取得: 複数社から見積もりを取り、比較検討。
適切な解体工事会社の選定は、スムーズな工事進行と満足のいく結果を得るための第一歩です。
丁寧に情報を収集し、検討を重ねることが重要です。
解体業者に見積もり依頼をする

解体工事の実際の費用を把握するためには、解体業者に見積もりを依頼することが必要です。
初めに、おおまかな見積額を知ることができる基本情報を提供することから始めましょう。
以下の6つの情報があれば、大体の金額を見積もることが可能です。
- 建物の場所(住所): 解体を行う建物の正確な位置情報。
- 建物の構造: 建物が木造、鉄骨造、RC(鉄筋コンクリート)造など、どのような構造か。
- 建物の面積: 解体する建物の広さ。
- 建物付近の道路幅: 建物へのアクセスに使われる道路の幅。
- 隣接する建物との距離: 近隣との距離が近い場合、特別な配慮が必要。
- 建物以外での処分を依頼するもの: 建物以外に解体や撤去を希望する物。
これらの情報をもとにした見積もりは、あくまで概算です。
正確な金額を知るためには、これらの情報を基に解体業者が現地調査を行う必要があります。現
地調査では、実際の状況を詳しく把握し、より正確な見積もりを提出してくれます。
現地調査を依頼する

解体業者に実際の建物状況を診てもらうことで、より正確な工事費用の見積もりを得ることができます。
建物の解体には、その構造や周辺環境の詳細な調査が必要不可欠です。
以下の理由から、現地調査は解体計画の初期段階で必ず行うべきです!
- 建物の構造や状態を正確に把握するため。
- 取り壊し手順や必要な機械、作業員の数を決定するため。
- 建物周辺の環境やアクセス方法を評価するため。
- 予期せぬ問題や追加工事が必要になるリスクを最小限に抑えるため。
現地調査をおろそかにすると、工事中や完了後に追加費用が発生するリスクが高まります。正確な計画と見積もりのために、信頼できる解体業者に現地調査を依頼しましょう。
家財整理を進める

解体業者を決定した後、次に行うべきは家財整理です。現地調査時に、解体業者に処分を依頼するものと自身で処分するものを明確に決め、工事着工前の1週間前までには整理を完了させましょう。
家財整理のポイント
- 内外の片づけ:不要なものを分別し、処分します。
- 粗大ゴミの処理:自治体に回収を依頼します。
- 家電・パソコンの処分:購入店に引き取りを依頼します。
- 設備の取り外し:再利用する設備は専門業者に依頼します。
- 庭の整理:雑草の除去や不要な庭木の伐採を行います。
適切な手配を行うことで、費用を抑えることができます。
安全に注意しながら、可能な範囲で家財の整理を行いましょう。
大型家具などの一般廃棄物は、解体工事会社が処理できないため、事前に自身で処分方法を確認してください。
解体工事に必要な各種届出
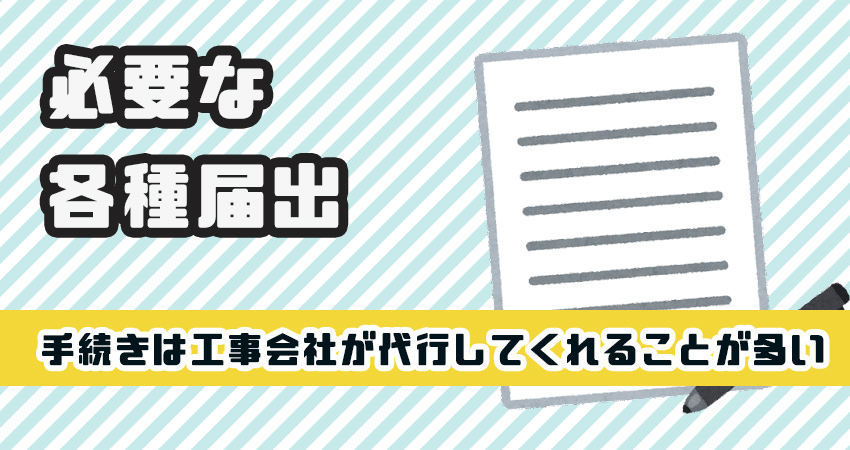
解体工事を行う際には、以下のような届出や申請が必要になることがあります。
これらの手続きは、法的な義務を果たし、工事をスムーズに進行させるために欠かせません。
- 建設リサイクル法の届出: 80㎡以上の建物を解体する場合、着工1週間前までに地方自治体に届け出る必要があります。
- 特定建設作業実施届: 解体工事が特定建設作業に該当する場合、事前に届出が必要です。
- 石綿事前調査結果報告: 建物に石綿(アスベスト)が含まれている可能性がある場合、解体前に調査を行い、その結果を報告します。
- 道路使用許可申請: 公道を使用する際には、管轄警察署での道路使用許可申請が必要になります。
これらの手続きは工事会社が代行してくれることが多いですが、自身で届け出が行われているかどうかを確認することが重要です。
手続きの完了は、工事を円滑に進行させるために必要不可欠です。
ライフラインの停止

解体工事をスムーズに進めるためには、工事開始1週間前までに電力、ガスなどのライフラインを停止する必要があります。
水道は、工事中に使用しますので、停止しなくて良いです。
以下の手順に従って、適切な手続きを行いましょう。
- 電気・ガス・電話の停止手続き: 電力会社やガス会社、電話会社に連絡し、解体工事の日程を伝えてサービスの停止を依頼します。
- 配管や配線の撤去手配: 工事中の事故を防ぐため、ガス管や電線などの引込配管、配線の撤去を手配します。これは安全対策の一環です。
- 浄化槽の汲み取り: 浄化槽を使用している場合は、汲み取りを行い、適切に処理する必要があります。
- 転居に伴う手続き: 転居届や郵便の転送届出、健康保険・国民年金の移転届けなど、転居に伴う各種手続きも忘れずに行いましょう。
これらの手続きは、工事担当者に代行を依頼することも可能です。不明点があれば、事前に相談してみてください。
近隣への挨拶と事前周知
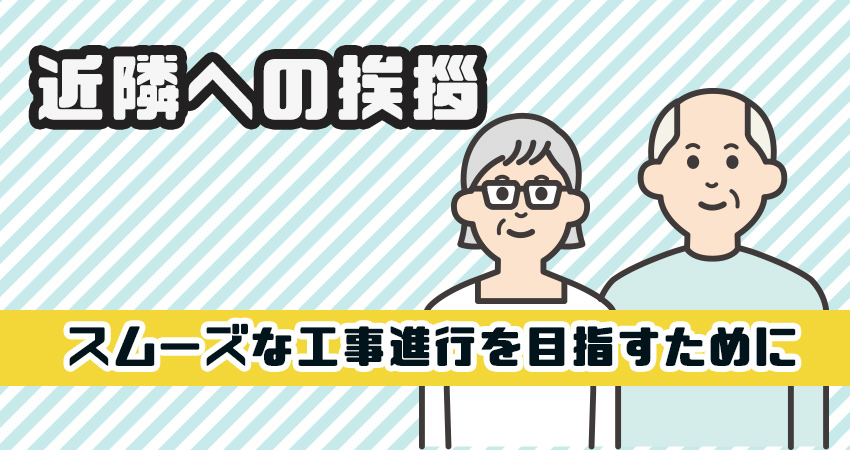
解体工事によって発生する騒音や振動、粉塵、埃、車の往来などは、近隣住民に迷惑をかけることがあります。
トラブルを避け、スムーズな工事進行を目指すためには、十分な説明と挨拶が必要です。
- 工事内容の説明: 工事の内容、予定されている工期、工事中に予想される影響などを明確に説明します。
- 挨拶の実施: 工事責任者と共に、近隣住民のもとへ粗品を持って挨拶に伺います。この際、工事に関する質問や懸念に対応できるよう準備をしておくことが大切です。
- 連絡先の提供: 工事中に何か問題が発生した場合には、すぐに対応できるよう連絡先を伝えておきます。
- 事前周知の徹底: 工事開始日や大きな騒音が予想される日など、重要な情報は事前に周知しておきます。
十分な説明や挨拶を行うことで、近隣住民との良好な関係を築き、クレーム発生のリスクを減らすことができます。解体工事は地域社会に大きな影響を与えるため、社会的責任を果たすことが求められます。
解体工事の着工

すべての準備が整えられ、解体工事が始まります。
一般的に、80㎡前後の建物の解体は約2週間で完了します。
解体プロセスは、屋根や内装の解体から始まり、次に建物本体の解体、最終的には建物基礎の解体と進行します。
- 屋根・内装の解体: 最初に屋根材や内装材の撤去を行います。
- 建物本体の解体: 構造体を順番に解体していきます。
- 建物基礎の解体: 最後に、建物の基礎を解体し、敷地を平らにします。
注意点
建物基礎の解体中に地中埋設物が発見されることがあります。
これらの発見は予期せぬ追加費用の原因となる場合があるため、解体工事会社と事前に処理方法について確認しておくことが重要です。
解体工事は計画的に進められますが、予期せぬ発見や事態にも柔軟に対応できるように、事前の準備と連携が鍵となります。
工事完了後

解体工事が終わると、最後に行うべきは工事現場の整地と、工事の内容が契約に沿って完了しているかの最終確認です。
工事現場の整地
掘り起こした地面はきれいに整地され、工事現場は整然とした状態に戻されます。
これにより、次のステップ、例えば新たな建設プロジェクトや土地の他の用途への移行がスムーズに行われます。
最終確認
- 工事内容の確認: 依頼者は、工事責任者と一緒に工事が契約書に記載された内容と相違がないかを確認します。
- 不備の確認: もし不備があった場合は、解体業者に修正を依頼する必要があります。
- 最終報告書: 工事の完了を示す報告書や、必要に応じて発行される証明書などを受け取ります。
工事の全プロセスが終了し、すべてが契約通りに行われたことを確認した後、解体工事は正式に完了となります。
この最終確認は、後日のトラブルを避けるためにも重要です。
マニフェストの受領

解体工事が完了したら、解体工事会社からマニフェスト(取り壊し証明書)を受け取ります。
このマニフェストは、建物が正式に解体されたことを証明する重要な書類であり、滅失登記を行う際に必要になります。
マニフェストの重要性
- 法的証明: マニフェストは、建物が解体されたことを公的に証明するための法的な書類です。
- 滅失登記の必要書類: 建物の滅失登記を行う際に、このマニフェストが必要となります。
マニフェストを受け取った後は、滅失登記の手続きを進めることができます。
この登記は、法的に建物が存在しなくなったことを証明し、土地の所有権や利用権の問題をクリアにするために重要です。
解体工事会社からマニフェストを受け取る際は、内容を確認し、必要な手続きのために安全な場所に保管してください。
地方法務局で建物滅失登記

建物が解体され、登記されていた建物が実際には存在しなくなった場合、地方法務局にその旨を届け出、建物滅失登記を行う必要があります。
この登記は、建物解体から1ヶ月以内に行う必要があります。
手続きの方法
- 自身での登記: 自分で手続きを行うことが推奨されますが、不安な場合は専門家に依頼することも可能です。
- 専門家による登記: 土地家屋調査士などの専門家に登記を依頼することもできますが、その場合は4~6万円程度の費用がかかることがあります。
- 解体工事会社のサポート: 一部の解体工事会社では、滅失登記の手続きサポートを提供している場合があります。不明な点がある場合は、解体工事会社に相談してみましょう。
建物滅失登記を行うことで、不動産登記簿が現状に合わせて更新され、将来的な不動産取引や法的問題を避けることができます。手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

